スマイルゼミと公文(くもん)のどちらが良いか悩んでいる方におすすめを解説します。
娘はスマイルゼミと公文を併用しています!公文は8学年の先取り学習中です。
スマイルゼミと公文の共通は『先取り学習』…のみ!その他は全く異なります!
スマイルゼミは2022年の4月から幼児コースと小学生コース限定で先取り学習が可能な「コアトレ」という新サービスがスタートします。詳しい内容は4月以降になりますが、コアトレの最新情報も踏まえて、併用中のスマイルゼミと公文を比較していきます!

資料請求は無料なので、ぜひ申し込んでみましょう!
幼児でも小学生コースを申し込んでも可能です!以前に申し込んだ方でもOK!
今なら、お風呂ポスターがもらえます!
幼児コース:ひらがなや数字、アルファベットのお風呂ポスター
小学生コース:世界の国旗や掛け算のお風呂ポスター
11/17(月)まで!
スマイルゼミと公文(くもん)特徴は先取り
スマイルゼミと公文の唯一とも言える共通の特徴は「先取り学習」です。その詳細をご紹介していきます。
スマイルゼミも公文も幼児期から先取り可能
| スマイルゼミ幼児コース | 公文 | |
| 対象年齢 | 年中(4歳・5歳)〜小学6年生 | 3歳〜 |
スマイルゼミは、2022年4月から「コアトレ」という無学年学習=先取り学習が始まります。
この新サービスは、スマイルゼミ幼児コース(幼稚園年中から)と小学コース限定で、中学3年生までの学習を先取り学習出来ます。
スマイルゼミはタブレット教材ならではのメリットである自動添削があります。そのため、子供が一人で取り組んでも無理なく先取りが進みます。
スマイルゼミの先取り「コアトレ」に関する記事はこちらもご覧ください。

公文は、一般的に3歳から始められます。ベビーくもんとは異なる公文式は教室によっては1歳からのところもあります。
ちなみに、娘は2歳過ぎから公文を始めて現在幼稚園年少で8学年先取りになりました!
公文は教室に通うため毎回先生によって進むか戻るか、先取りするかの判断があります。
スマイルゼミと公文(くもん)教科比較
スマイルゼミ幼児コースと小学生コースは、学べる分野がたくさんありますが、公文と比較するために国語・算数・英語を比較したいと思います。
先取り学習(コアトレ)が可能な教科は国語と算数です。
スマイルゼミと公文を教科で比較すると、算数が一番大きな比較対象になります。
公文の算数は、計算がメインで有名です。計算しかしません。一方、スマイルゼミは計算ドリルという計算だけのものもありますが、毎月配信されるものは、算数といえど文章問題やその他の問題も豊富です。
それでは、各教科を見て比較していきましょう!
スマイルゼミの教科


- スマイルゼミ幼児コース
「ひらがな・カタカナ・ことば・えいご・ちえ・かず・かたち・とけい・せいかつ・しぜん」が学べます。
- スマイルゼミ小学生コース
小学生コースは教科書準拠なので、学校の授業に沿った学びが可能です。プログラミングもあります。
どちらのコースも『コアゼミ』では、国語と算数が中学レベルまで先取り出来ます!
スマイルゼミの国語




- 文字・漢字
- 言葉
- 分のしくみ
この3つを主に幼児コースも小学生コースも中学レベルまで先取り学習が出来るようになっています。
通常のスマイルゼミの国語(小学一年生)は、文章問題や漢字などしっかり出来るようになっています。


漢字に関しては、毎月の漢字学習に加えて『スマイルゼミ漢検ドリル』で、さらに学習することが可能です。


漢検ドリルは追加受講料なしで、漢字検定10級から2級までの先取り学習が出来ます。
とてもお得なサービスです!詳細は下記の記事を参考にしてください。


スマイルゼミの算数




コアトレはまだ始まっていないため詳細は2022年度4月以降になりますが、
- 計算
- 数量
- 図形
この3つを主に幼児コースも小学生コースも中学レベルまで先取り学習が出来るようになっています。
通常のスマイルゼミの算数(小学一年生)は、文章問題や計算など幅広く出来るようになっています。
例えば、1ヶ月間に算数の問題もこんなにたくさんあります。何度でも繰り返し出来るところがタブレットのメリットです!


文章問題もあります。
問題を読んで式と答えを導き出します。


毎月の算数とは別に「計算ドリル」と呼ばれる計算に特化したプログラムがあります。
一番最初に出てくる足し算の問題は下記のイメージ通りです。時間内にどんどん解いてきます。
繰り返すうちに、暗算力が付いてきます。


計算ドリルの6級は小学1年生です。以下の通り9つの問題を解きます。その後に、5級小学2年生、4級、3級…….と進むことが可能です。
- 足し算
- 引き算
- 10より大きい数
- 3つの数の計算
- 繰り上がりのある足し算
- 繰り下がりのある引き算
- 大きな数の計算
- 6級のまとめ
- (対戦25マス計算)
スマイルゼミは毎月の算数問題に加えて、計算ドリルで計算力も付いてボリュームたっぷりの内容です。
タブレット教材で算数に特化したい場合は、RISUきっず(幼児向け)、RISU算数(小学生向け)もあります。
算数に関してはスマイルゼミとRISU算数の比較記事があります。
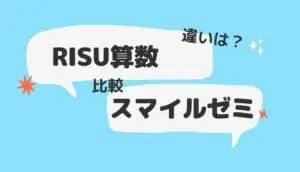
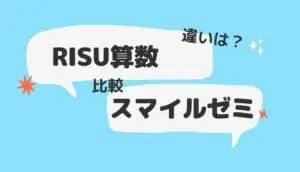
RISU算数の詳細は下記の記事を参考にしてください。


スマイルゼミの英語


スマイルゼミの英語には定評があります!
最新の英語教材の顧客満足度調査では、幼児向け英語教材では「優秀賞」小学生向けの英語教材では「最優秀賞」を受賞しています。
例えば、英語も発音を聴いたりするだけではなく、自分でも言ってみて、実際の発音と自分の発音を比べることが出来ます。
スピーキングの練習をしっかり取り組めるのもスマイルゼミの特徴です。
英語にさらに力を入れたい場合は、追加プログラムで『英語プレミアム』があります。毎月の英語配信に加えて、さらに英語のプログラムが加わります。
レベルは、HOP(小学校低学年相当)とSTEP(小学校中学年以上相当)があります。
スマイルゼミ英語プレミアムの口コミはこの記事も参考にしてください。


公文の教科
公文のメインの教科は国語・算数・英語です。(ドイツ語などの外国語もあります。)
公文は全て紙のプリント教材で、どの教科も1レベル200枚と決まっています。国語のみレベルA(小学1年生レベル)からAIとAIIの200枚200枚、全部で400枚となっています。
公文は週に2回の教室通いと毎日の自宅学習です。1レベルが200枚で宿題は毎日5枚が基本なので、単純計算すると40日で1つのレベル(1学年)の学習内容が終わるようになっています。
公文の国語


公文の国語は8Aから始まりAIからが小学一年生の内容に相当します。
娘は2歳過ぎで公文を始めて現在幼稚園生で小学生の学習内容まで先取りが進んでいます。


公文は幼児向けはカラープリントですが、もちろんキャラクターもありません。
学習内容が難しくなってくるとプリント自体白黒になります。
ひらがなをひたすら覚えたら、カタカナ、短文から長文、漢字が始まり文章題…など、単元ごとに教材のねらいがあるので、とにかくプリント数をこなしていきます。
学習は先取りすることも戻ることも可能です。
教室に通うため、先生に進度を確認してもらいプリントが決まります。
公文の算数


公文の算数は幼児対象の6Aから始まり、Aが小学1年生に当たります。Bが小学2年生と1つずつ学年が上がります。
算数も国語同様、幼児向けプリントはカラーで若干のイラストはあります。
学年が上がるごとに淡白な内容になります。
公文の算数は計算が基本なので、計算ばかりです。たまに、文章問題があるくらいです。


公文の算数は幼児対象の3Aから足し算が始まります。
足し算が始まると、裏も表も足し算の式だけになります。それが進むと引き算、掛け算、割り算…
下記は分数の計算ですが、このように連番でずっと計算のみです。公文の特徴は計算力なので、このような繰り返しで計算力が身に付くようになっています。


計算のみなので算数という点では、偏ってはいます。
図形や文章問題など一緒に取り組みたい場合は、スマイルゼミやRISU算数の方が良いです。
公文の英語




公文の英語はGIが中学一年生の英語に相当します。
イーペンシルと呼ばれるタッチペンで教材をタッチしてリスニングをします。
幼児期はタッチペンで単語の発音を聞いて自分でも発音してみることがメインです。
進むにつれて、アルファベットの書き取りから始まり、徐々に文法がメインになります。
タッチペン教材というと、通信教育のポピーKids Englishもあります。小学3年生までの英語学習が毎月1,680円です。
こちらの記事も参考にしてください。


スマイルゼミと公文(くもん)学習の違いを比較
スマイルゼミも国語と算数の先取りが始まるため、スマイルゼミと公文は先取りという点で同じですが、それ以外は全く異なる教材です。
勉強スタイルも勉強の内容も全く異なるため、しっかりと比較しましょう。
スマイルゼミはタブレット教材で総合学習
スマイルゼミはタブレット教材のみの総合学習です。どれか1教科だけを受講することは出来ません。
幼児コースは全10テーマ、小学生コースは教科書準拠です。
スマイルゼミは各教科幅広く学べる上に、算数なら「計算ドリル」国語なら「漢字ドリル」と特化した学びも可能です。
タブレットなので、一人学習が可能です。自動添削なので学習がどんどん進みます。
公文はプリント教材で各教科
公文はプリント教材で1教科ずつ受講します。
教室に通う場合は、週に2回通い宿題をもらえます。
先取りするか戻るかは先生の判断によります。
毎日宿題(基本的に1教科1日5枚)を自宅で取り組み、教室で提出して先生に採点してもらいます。
1レベル200枚を終えた後、終了テストを受けて合格すると次のレベルに進むことが可能です。
スマイルゼミと公文(くもん)料金の比較
| 学年 | 公文(東京都・神奈川県) | 公文(その他の地域) | スマイルゼミ |
|---|---|---|---|
| 幼児 | 7,700円 | 7,150円 | 3,278円 |
| 1年生 | 7,700円 | 7,150円 | 3,278円 |
| 2年生 | 7,700円 | 7,150円 | 3,520円 |
| 3年生 | 7,700円 | 7,150円 | 4,180円 |
| 4年生 | 7,700円 | 7,150円 | 4,840円 |
| 5年生 | 7,700円 | 7,150円 | 5,720円 |
| 6年生 | 7,700円 | 7,150円 | 6,270円 |
※スマイルゼミは12ヶ月一括払いの場合の金額
公文は1教科あたり7,150円〜に対して、スマイルゼミは全教科なので、学習内容と学習量で見ると圧倒的にスマイルゼミの方がお得に感じます。
一方、スマイルゼミはタブレット教材なのに対して、公文は教室に通い、先生に見てもらうという点が大きく異なります。
スマイルゼミのキャンペーン情報を駆使して安く入会できる方法はこちら!


スマイルゼミと公文(くもん)親の負担を比較
子供が小さいうちは特に子供の勉強は親の負担になります。
娘が併用中なので、私の率直な感想をご紹介します!
スマイルゼミはタブレット教材で最小限
スマイルゼミはタブレット教材なので、親の負担は最小限です。
- その日のやるべき内容が出題される
- 自動添削
- 分からない時はヒントを教えてくれる
- 間違えたら教えてくれる
全て自動で進めてくれるので、子供一人でもしっかり取り組むことが可能です。
最初の頃は使い方に慣れなくても、すぐに一人で出来るようになります。
家事の合間でも、子供一人でしっかりと取り組めます。
公文は親の負担が大
公文はとにかく「親の忍耐力」です!親の負担が多いところが特徴です。
1日5枚といえ、紙教材なので親が付きっきりで見る必要があります。
分からなければ、親が教えることが必須です。また単調なプリント内容なため、子供の集中力が切れることが多々あります。
そんな時に常に親が声掛けしたりと、親の時間の余裕と取り組む余裕が必要になってきます。
スマイルゼミと公文(くもん)比較まとめ【メリット・デメリット】
これまでの内容の比較(メリットデメリットも!)を踏まえてまとめました。
スマイルゼミおすすめな人【メリット・デメリット】
この3つはメリットでもあり、おすすめな人です!
- 総合的な学びをしたい!
- 先取りに興味がある!
- 一人でしっかり取り組める!
一方、スマイルゼミのデメリットはこちら。
- 好きな教科だけをやってしまう
公文おすすめな人【メリット・デメリット】
この3つはメリットでもあり、おすすめな人です!
- 先生の指導を受けながら学習したい!
- 先取りに興味がある!
- 紙プリントでしっかり学習したい!
一方、公文のデメリットはこちら。
- 毎日の宿題が大変(保護者が手伝えない)
- プリントが溜まってしまい困る
- 同じことの繰り返しで飽きてしまう
スマイルゼミと公文は比較してみると違いがたくさんありますね♪


資料請求は無料なので、ぜひ申し込んでみましょう!
幼児でも小学生コースを申し込んでも可能です!以前に申し込んだ方でもOK!
今なら、お風呂ポスターがもらえます!
幼児コース:ひらがなや数字、アルファベットのお風呂ポスター
小学生コース:世界の国旗や掛け算のお風呂ポスター
11/17(月)まで!
